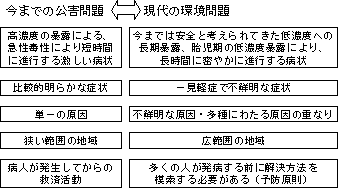
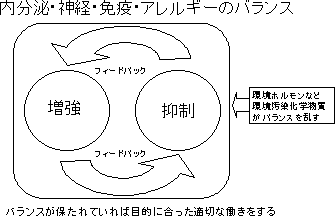
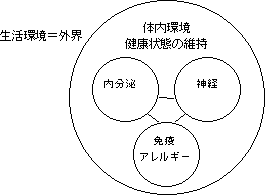
<№03-13 2000年10月30日公開>
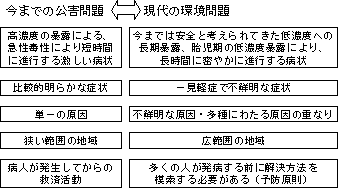 |
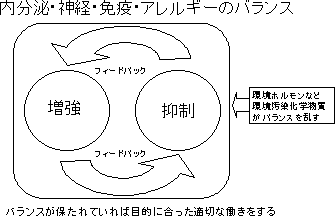 |
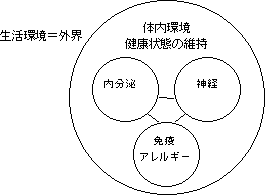 |
地球上の生物は、全て地球の環境の中で生存をしています。あたりまえのように暮らしているこの環境は、非常にまれな確率で出来上がりました。水が液体の状態でいられる適温に灼熱の大地が冷えたこと、光合成を行なって太陽の光と水と二酸化炭素から酸素を生み出す植物細胞が水の中で生まれたこと、酸素がオゾン層をつくり太陽の紫外線を減らしたことなど様々な偶然が重なり、生物にとって好適な環境になった結果、現在の地球上に生物の繁栄をもたらしました。生物達は長い時間をかけ、酸素を利用し、酸素の毒性(活性酸素)を処理できる能力を獲得しました。自らの能力や姿を変えて環境に適応することで、健康状態を維持し、子孫を残し、生命の鎖をつなぎました。生物たちが生存可能な環境を求め、羽や足を使い移動することはあっても、限りがありました。ところが、人間は新たな化学物質を次々と作り出し、環境に手を加えることで、環境に適応しました。新たな化学物質は、人間に便利さ・快適さをもたらし、特に、産業革命以後、その生産は急激に進み、様々な化学物質で環境はあふれました。今までに人類が生み出した化学物質は1200万種以上と言われ、そのうち一般に使用されている化学物質は10万種に及びます。今までに人類が生み出した化学物質は1200万種以上と言われ、そのうち一般に使用されている化学物質は10万種に及びます。微妙な偶然で出来上がり、一定の状態を維持してきた地球環境は、急激な変化を起こし、危機的な状態に陥ろうとしています。公害、二酸化炭素等による地球温暖化、フロンガスによるオゾン層の破壊、ディーゼル車排気中の微細な炭素粒子(diesel exhaust particles,DEP)による大気汚染、化学物質による室内汚染、外因性内分泌かく乱物質(環境ホルモン)等の化学物質による生殖・内分泌・神経・免疫機能の失調など様々な問題が明らかになりつつあります。地球上の生物は劇的な変化の中で健康状態を崩し始めました。人間も例外ではありません。
人類を含め全ての生物は環境中からエネルギーを獲得し、老廃物を環境中に排泄しています。体内と環境(外界)は巧みに隔離され、内分泌・神経・免疫(アレルギー)の働きにより、常に最良の状態に保たれています(つまり、健康ということ)。特に、哺乳動物はその巧妙な能力により、過酷な環境にも適応できる力を持っています。しかし、適応能力には限界があり、あまりに急激な変化、広汎な変化の場合には、適応できずに病気を起こしてしまいます。
現在進行中の環境問題は、今までの公害問題・環境問題とは様相が異なっています。急性毒性によって狭い範囲の地域で引き起こされる激しい症状ではなく、今までは安全と考えられてきた低濃度の化学物質への長期暴露、胎児期・乳児期の低濃度暴露によって広範囲の地域で一見軽症な症状や病気が密やかに進行します。単一な原因ではなく、不鮮明で、多種にわたった原因の重なりの中で健康被害が進行します。したがって、正確な情報と正確な知識、緻密な観察力と診断能力が必要であり、住民、医療従事者、科学者など様々な人達が協力して事態の予防と対策にあたる必要があります。現状では、様々な野生動物が環境汚染化学物質の影響を受けていることがわかってきています。しかし、まだ人における影響の確実な証拠はつかめていません。一方では、環境の悪化とその影響の因果関係がはっきりしたときには、人類や地球上の生物の生存は脅かされ、すでに遅いのではないかと考えられています。病人が発生してからではなく、多くの人が発病する前に解決方法を模索する必要があります。人々や野生動物がおかれた環境の悪化に敏感に察知し、予防原則に基づいた迅速で適切な行動をとり、環境の悪化を未然に防ぐ必要があるのです。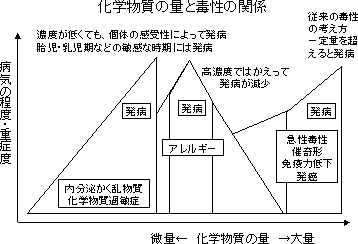
従来は、化学物質の量が増えれば、毒性が増し、健康被害(急性毒性や発癌、催奇形性など)を受けると考えられてきました。しかし、外因性内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)や化学物質過敏症などでは、この考え方は当てはまりません。極微量でも、内分泌のかく乱や過敏症を起こします。アレルギー性疾患でみても、自然物(食べ物や花粉など)に微量の汚染がある場合はアレルギーを起こし、高度の汚染の場合にはアレルギーさえも起こせず、免疫力低下(感染しやすい)となって現れたり、奇形を起こしてしまう可能性があります。今まで、一般的に使われてきた「濃度○○以下は安全」という定義は、通用しなくなってきているのです。
また、胎児や乳児など感受性の高い時期にどの程度の汚染なら安全なのかという認識は、今までの毒性評価には使われてきていません。今、問われているのは、胎児・乳児の安全性であり、この観点から様々な化学物質の毒性が再評価されなければいけません。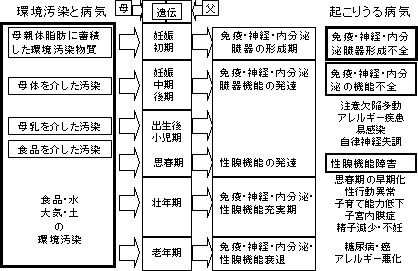
さらには、胎児期に限らず、出生後の成長期各段階において、様々な臓器に様々な影響を与える可能性があり、今後の研究が待たれます。環境汚染によって起こりうる疾病の主なものを表に記しました。
「“動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質”を意味する。近年、内分泌学を始めとする医学、野生動物に関する科学、環境科学等の研究者・専門家によって、環境中に存在するいくつかの化学物質が、動物の体内のホルモン作用を攪乱することを通じて、生殖機能を阻害したり、悪性腫瘍を引き起こすなどの悪影響を及ぼしている可能性があるとの指摘がなされている。これが『外因性内分泌かく乱化学物質問題』と呼ばれているものであり、環境保全行政上の新たで重要な課題の一つである。」(1998年5月環境庁 環境ホルモン戦略計画SPEED‘98より)
環境ホルモン(外因性内分泌撹乱物質)は、以下のような特徴を持っています。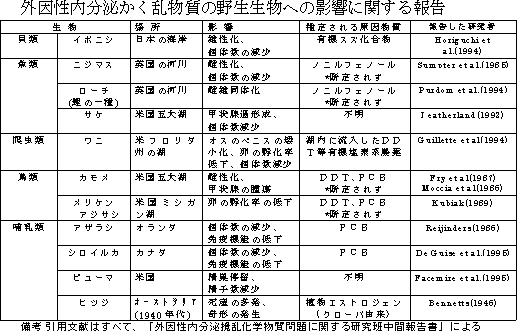
1)生物の体内で、ホルモン(内分泌)と同じように作用し、生殖機能などの正常な働きをかく乱する物質、
2)野生動物では、生殖器の異常、子育ての放棄、メス同士のつがい、卵の孵化率減少などが報告されている、
3)ホルモンは極微量で体をコントロールしているため、環境ホルモンも極微量で作用する、
4)人間への影響は内分泌機能の変調、神経の働きの障害、とくに自律神経の失調、免疫力の変調、アレルギー反応の変調、乳ガン、前立腺ガン、生殖機能の低下、不妊症、流産、精子減少、子育て能力の低下、行動異常(多動、注意力の低下、学習障害、乱暴な行動、過剰な反応など)、運動機能や
知能への障害などが考えられている、
5)特に胎児(とくに胎児期初期)、乳児期にさらされると影響が大きい、
6)農薬やダイオキシンの他に、今まで安全と思われていた化学物質も環境ホルモン作用を有する、
7)どのくらいの摂取量なら安全かは未解明、
8)様々な生物が環境汚染化学物質から受けているかく乱作用は、すべて細胞が発した信号を目的とする細胞に正確に伝達できないで起きる現象であり、細胞間信号伝達かく乱作用ともいうべきものである。今後研究が進み、神経や免疫を中心に異常を起こす場合は、外因性神経かく乱物質、外因性免疫かく乱物質という名称が使われるようになると思われる。
野生動物に対する化学物質の影響は表のごとく様々な報告がされています。しかし、化学物質とに因果関係は確定できないものが多く、ヒトの健康に対する化学物質の影響では更に因果関係を特定できる可能性は低くなります。
1998年5月環境庁「環境ホルモン戦略計画SPEED‘98」では内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質として67種類をあげています。1977年3月通産省「内分泌系に作用する化学物質に関する調査報告書」では107種類を掲げました。(社)日本化学工業会では、さらに広く精査し多くの143種類の化学物質をリストアップしました。
参考 Deborah Cadbury著:メス化する自然 P.268
●環境中のエストロゲン(女性ホルモンの働きをする化学物質)
メトキシクロル(有機塩素系殺虫剤:1960年日本国内の農薬登録失効、1985年水質・底質調査で残留なし)、一部のPCB類(有機塩素系化合物:熱媒体・ノンカーボン紙・電気製品に使用、1954年から1971年に57300tが生産された、1972年生産中止、環境中に広く残留)、リンデンのβ-異性体(有機塩素系殺虫剤:1971年農薬登録失効。環境中に広く残留)、DDT(有機塩素系殺虫剤:1981年製造・販売・使用中止、環境中に広く残留)、ビスフェノールA(ポリカーボネート樹脂・エポキシ樹脂・フェノール樹脂の原料、1997年環境中に広く残留が見つかる、合成樹脂製哺乳ビン・缶詰内面の被膜に使用されている)、オクチルフェノール(フェノール樹脂の原料、界面活性剤に使用)とノニルフェノール(アニオンおよび非イオン界面活性剤、工業用洗剤などに使用)/アルキルフェノール・エトキシレート
●抗エストロゲン(抗女性ホルモン)化学物質
ダイオキシン(有機塩素系化合物)、p,p'-DDE(有機塩素系殺虫剤DDTの分解物:鳥類でエストロゲンの減少を促進)、エンドサルフアン(有機塩素系殺虫剤:農薬として使用中。魚でビテロゲニン生成を阻害)
●抗アンドロゲン(抗男性ホルモン)化学物質
p,p'-DDE、ダイオキシン類、ビンクロゾリン(殺虫剤:チェリーや輸入キウイに使用、アンドロゲンレセプターと結合)、HPTE(2,2-ビス[p-ハイドロキシフェノール] -1,1,1-トリクロロエタン:メトキシクロルの代謝物)、p,p'-DDE
●甲状腺ホルモンかく乱物質
PCB類、ダイオキシン類、鉛、チオカルバミドをベースにした農薬(ジチオカーバメイト剤:アンバム、カーバム、ジネブ、ジラム、チウラム、メチラム、ポリカーバメート、マンゼブ、マンネブなど)、あるいはスルホンアミドをベースにした農薬(スルファミン酸塩・アンモニウム塩:イクリン、ショーメイト、マイセフティなど)、
PPB類(ポリ臭化ビフェニール:難燃剤として年間30t生産され使用中)、
フタル酸エステル(塩化ビニルなどの合成樹脂の可塑剤として多量に使用中)
へキサクロロベンゼン(有機塩素系殺菌剤:1972年製造・販売・使用禁止、環境中に残留あり)
●副腎皮質ホルモンかく乱物質
ビンクロゾリン及び関連の殺菌剤、アニリン染料、四塩化炭素、クロロホルム(水道水中に発生するトリハロメタン)、DDT及びDDE、ジメチルベンゾアントラセン(DMBA)、メチルアルコールおよびエチルアルコール、窒素酸化物、PCB類、PBB類、ケトコナゾール(抗真菌剤)などの殺菌剤、トキサフェン(有機塩素系殺虫剤:日本では農薬登録なし)など
内分泌かく乱物質のヒトへのリスク分類:リスク(ヒトへの影響)が高い順に並べてある
| 分類 | 物質名 | 健康被害 | 環境への排出 | 残留性 | 内分泌かく乱作用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境中への排出はすでに禁止されている有機塩素系化合物、有機スズ化合物の一部 | DDT、PCB、HCHなど トリブチルスズ、トリフェニルスズ |
過去に大量に生産・使用され、生態系への影響や健康被害が明らか | 1970年代~生産・使用が中止された | 残留性が高く、現在も環境中や人体に検出されている | 確定 |
| 現在、環境への排出を減らす努力がされている化学物質 | ダイオキシン類、ベン(a)ピレン、鉛、カドミウム、水銀 | 過去に重大な環境問題を起こしている | 現在も環境中に排出されている | 残留性が高く、環境中に検出される | 確定 |
| 現在も使用されている有機塩素系農薬 | エンドスルファン、ジコホル、アトラジンなど | 内分泌かく乱作用は分かっているが、現在も使用されている | 環境中に排出されている | 残留性が高く、環境中に検出 | 確定 |
| 現在も使用されている非有機塩素系農薬 | カーバメイト、ジチオカーバメイト、ピレスロイド、有機リン系殺虫剤など | 内分泌かく乱作用が疑われているが、現在も使用されている | 環境中に排出されている | 環境中に検出 | 疑われている |
| ホルモン作用を発揮することを期待して使われる医薬品(DESは使用中止) | 合成女性ホルモン(DES、ピル、子宮頸管熟化剤など)、副腎皮質ホルモン、抗真菌剤など | 内分泌への作用を期待して使用される | 環境中に排出されている | 環境からの検出は不明 | 確定 |
| プラスチック製品およびその添加物、合成洗剤 | ビスフェノールA、フタル酸エステル、ノニルフェノール、スチレンなど 有機臭素系難燃剤など |
日常の使用量で健康被害が起こるか否かで論議が分かれている | 多量に使用され環境中に排出されている | 環境中に検出 | 動物実験ではほぼ確定されているが作用が弱い |
| 植物に含まれるホルモン(エストロゲン)作用物質 | 大豆に含まれるダイゼイン、ゲニステインなど | 不明。植物が自己防衛するために作り出している物質。他のエストロゲン作用化学物質の影響を軽減している可能性もある。 | 自然界で普通に存在 | 自然界で普通に存在 | 自然の状態から逸脱した食べ方をしない限り、問題はないと思われる |
これらの化学物質を、環境汚染の視点からヒトへのリスクとして考えた場合、表のように6つに分類できます。ヒトの健康に影響が強いと思われるものから順に並べてあります。
すでにヒトへの健康被害が明らかな化学物質(上3段)は、すでに生産・使用が中止されているものもありますが、環境中には依然存在し、脂溶性(生物の体脂肪に溶けこむ性質)であるため食物連鎖を介して生体内濃縮を起こし、様々な生物の生存を危うくさせています。とくに、ヒトの母乳中には今だかなりの濃度の残留があり、乳児の成長・発達と生命機能を脅かしています。
ヒトの場合、現状の食生活方法では食物連鎖を増やし、生体内濃縮を人工的に高める可能性が高いため、食料生産の方法や食べ方を見なおす必要を感じています。環境汚染物質が蓄積しやすい食物としては、脂の多い魚や魚卵、肉の脂・家畜の肝臓(レバー)、牛乳・チーズ・バターなど乳製品、卵、およびその加工品、植物性油脂などがあげられます。
「食物連鎖を飛び越え」、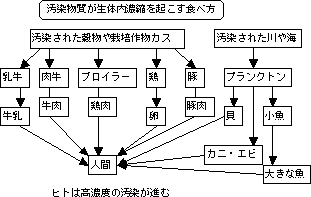 大地に生えた植物を中心に食べることが基本に置かれると汚染を受ける可能性が激減します。食物連鎖を増やす場合(家畜を生産する)には、汚染の少ない飼料を使う必要があります。汚染のある海や川で捕れた魚介類はなるべく食物連鎖の初期にいる生物、年齢が若い生物を食べることで汚染は軽くなります。この食べ方は、古くから米や野菜、味噌汁、野菜の漬物、お茶を中心にした日本の食生活の中に根付いてきたものです。
大地に生えた植物を中心に食べることが基本に置かれると汚染を受ける可能性が激減します。食物連鎖を増やす場合(家畜を生産する)には、汚染の少ない飼料を使う必要があります。汚染のある海や川で捕れた魚介類はなるべく食物連鎖の初期にいる生物、年齢が若い生物を食べることで汚染は軽くなります。この食べ方は、古くから米や野菜、味噌汁、野菜の漬物、お茶を中心にした日本の食生活の中に根付いてきたものです。
非有機塩素系農薬(表の4段目)、プラスチック製品およびその添加物、合成洗剤(表の5段目)の中には、胎児や乳児の脳神経の発達に影響するものも多く含まれ、使用量や使用場所、使用方法が再検討される必要があります。今後、様々な研究が進み、影響の実態がわかっていくと思われます。これらの化学物質に対しては予防原則にのっとり、疑わしき化学物質は使用を規制していくことが必要です。
ホルモン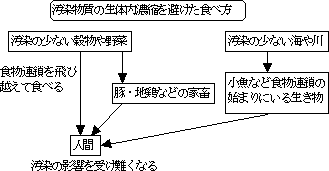 作用を利用した医薬品は、病態を十分把握して、適切に使用することが望まれます。その使用方法に関しては、「内分泌かく乱」という新たな視点を取り入れ、再検討すべきものもあります。低用量ピル、子宮頸管熟化剤などは使い方を誤ると、胎児に合成女性ホルモンを暴露させる可能性があります。
作用を利用した医薬品は、病態を十分把握して、適切に使用することが望まれます。その使用方法に関しては、「内分泌かく乱」という新たな視点を取り入れ、再検討すべきものもあります。低用量ピル、子宮頸管熟化剤などは使い方を誤ると、胎児に合成女性ホルモンを暴露させる可能性があります。
植物に含まれるホルモン(エストロゲン)作用物質は、その植物が自己防衛のために体内で生産しているもので、古来、自然界には存在し続けてきました。ヒトはその影響(効果)を避けるため、または利用するために植物を調理・加工して食べてきたのです。例えば、大豆には多くの植物エストロゲンが含まれますが、じっくりと煮こんで調理する、味噌やしょうゆ、豆腐、納豆などに加工することで植物エストロゲン作用を弱めながら食べる工夫をしてきました。環境中に、他のより強い影響力を持つエストロゲン作用物質が存在する場合には、植物エストロゲンはそれらと拮抗して悪影響を軽減させる可能性もあり、一概に健康破壊につながると考える必要はありません。日本人は古来、大豆など豆植物によって健康を維持してきているのです。